【すりこぎ徹底解説】あなたの料理を格上げする一本はどれ?選び方から使い方まで完全ガイド!
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「すりこぎって、どれも同じに見えるけど、本当に違いがあるの?」
「せっかく買うなら、長く使える良いものが欲しいけど、選び方がわからない…」
そんな風に感じていませんか。
キッチンに立つたびに、「このすりこぎで本当に良いのかな?」と疑問に思うことは、決して珍しいことではありません。
特に、素材の風味を最大限に引き出したいと願う料理好きの方にとって、すりこぎ選びは料理の仕上がりを左右する重要なポイントです。
この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消し、最高のすりこぎを見つけるための完璧な購入ガイドとなることをお約束します。
すりこぎの奥深さに触れ、あなたの料理がワンランクアップする体験をぜひ手に入れてください。
読み終える頃には、きっと「これだ!」と思える一本に出会えているはずです。
すりこぎの特徴と魅力を徹底解説!

すりこぎは、日本の食文化に深く根ざした伝統的な調理器具です。
そのシンプルな見た目からは想像できないほど、料理に豊かな風味と奥深い味わいをもたらします。
主な役割は、食材を「擂り潰す」「混ぜる」「練る」こと。
ごま和えの香ばしさ、味噌汁のまろやかさ、とろろのなめらかさなど、すりこぎがなければ表現できない独特の食感と香りを生み出すことができます。
人気の理由は、何と言ってもその「手作業ならではの繊細さ」にあります。
フードプロセッサーのような機械では得られない、食材の細胞をゆっくりと壊し、旨味や香りをじっくりと引き出すことができるのです。
例えば、ごまを擂る際、すりこぎを使えばごまの油分がゆっくりと滲み出し、香ばしさが格段に増します。
これは、高速で粉砕する機械では難しい、熱による風味の劣化を防ぎながら、丁寧に香りを引き出すことができるからです。
また、すりこぎは電気を使わないエコな調理器具であり、静かに作業できる点も魅力です。
早朝や深夜でも、音を気にせず調理に集中できるのは、忙しい現代人にとって大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、木製のすりこぎは使い込むほどに手に馴染み、愛着が湧く一生ものとなることもあります。
単なる道具としてだけでなく、料理の時間を豊かにするパートナーとして、その存在感は計り知れません。
すりこぎ一つで、いつもの料理がより美味しく、より楽しくなること間違いなしです。
種類と用途:あなたにぴったりのタイプは?
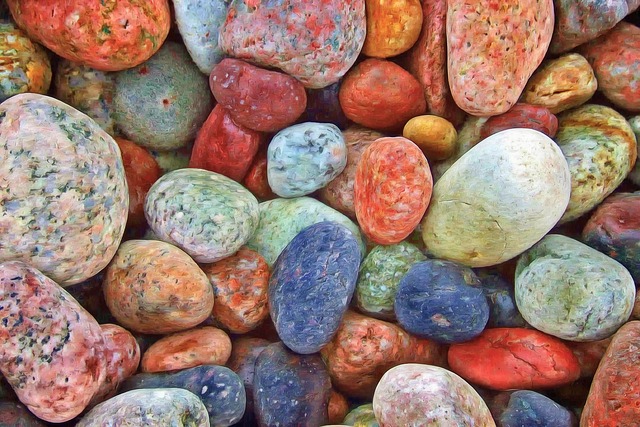
すりこぎと一口に言っても、その種類は多岐にわたり、それぞれに異なる特性と最適な用途があります。
自分にぴったりの一本を見つけるためには、まずそのバリエーションを知ることが重要です。
素材で選ぶすりこぎ
- 木製すりこぎ(山椒、朴の木、檜など)
- 特徴:最も一般的で、手に馴染みやすいのが魅力です。特に山椒の木は、その独特の凹凸が食材を効率よく擂り潰し、香りを引き出すのに優れています。朴の木や檜は、比較的柔らかく、食材への当たりが優しいのが特徴です。
- おすすめの人:本格的な和食を楽しみたい方、ごまや味噌を頻繁に擂る方、手作業の温かみを重視する方にぴったりです。
- 注意点:匂いが移りやすい、カビが生えやすいといったデメリットもあります。
- 陶器・セラミック製すりこぎ
- 特徴:表面が滑らかで、匂いや色が移りにくいのが大きなメリットです。お手入れも比較的簡単で、清潔に保ちやすいでしょう。
- おすすめの人:ハーブやスパイス、離乳食など、匂いの強いものや衛生面を重視する方におすすめです。
- デメリット:木製に比べて重く、落とすと割れる可能性があります。
- ステンレス製すりこぎ
- 特徴:非常に衛生的で、耐久性が高く、食洗機にも対応しているものが多いです。モダンなキッチンにも馴染みやすいデザインが特徴です。
- おすすめの人:手入れのしやすさや衛生面を最優先する方、スタイリッシュな調理器具を好む方に良いでしょう。
- デメリット:食材を擂る際の摩擦が少なく、木製に比べて擂り心地が物足りなく感じることもあります。
用途で選ぶすりこぎ
- 和食全般(ごま和え、味噌、とろろなど)
- おすすめ:やはり木製すりこぎが最適です。特に山椒の木は、ごまの香りを最大限に引き出し、本格的な味わいを求める方には欠かせません。
- 洋食・エスニック(ハーブペースト、ドレッシング、スパイス)
- おすすめ:陶器やセラミック製が向いています。匂いが移りにくいため、様々なハーブやスパイスを安心して使えます。
- 離乳食・介護食
- おすすめ:陶器やステンレス製が衛生的で安心です。食材をなめらかに潰しやすく、お手入れも簡単なので、忙しいママさんにもおすすめです。
このように、すりこぎは素材や用途によって選び方が大きく変わります。
あなたがどんな料理を作りたいのか、どんな点を重視するのかを考えながら、最適な一本を選んでみてもいいかもしれません。

石臼セット 天然花崗岩 スパイス 石臼 小型 すり鉢 すりこぎ棒 セット 薬研 キッチン用品 抗菌 健康 安全 乳鉢 料理 香辛料 調味料 離 食セット シリコン蓋付 多用途 ハンド研磨 磨かれた天然乳鉢 乳棒 家庭用
価格:5680円 (2025/10/7時点)
楽天で詳細を見る
性能で選ぶ!チェックすべきポイントはここだ!

すりこぎを選ぶ際、素材や用途だけでなく、その「性能」にも注目することで、より満足度の高い一本を見つけることができます。
ここでは、購入前にチェックすべき重要なポイントを分かりやすく解説します。
1. すりこぎの先端の形状と溝の深さ
- ポイント:すりこぎの先端には、溝(ギザギザ)が彫られているものが多く、これが食材を効率よく擂り潰すための鍵となります。
- 深めの溝:ごまやナッツなど、硬めの食材をしっかりと擂り潰したい場合に適しています。摩擦力が強く、短時間で細かくできます。
- 浅めの溝・滑らかな先端:豆腐や野菜など、柔らかい食材をなめらかにしたい場合や、混ぜ合わせる用途に向いています。
- 選び方:主に何を擂るかによって、先端の形状や溝の深さを確認しましょう。
2. 持ちやすさと重さのバランス
- ポイント:すりこぎは手で持って使うものなので、握りやすさや重さは非常に重要です。
- 握りやすい太さ:手の大きさや力の入れ具合に合った太さであるかを確認しましょう。細すぎると力が入りにくく、太すぎると握りにくいことがあります。
- 適切な重さ:軽すぎると力が伝わりにくく、重すぎると疲れてしまいます。適度な重さがあるものは、安定して作業を進められます。
- 選び方:可能であれば、実際に手に取って感触を確かめてみるのが一番です。
3. すり鉢との相性
- ポイント:すりこぎは単体では機能しません。すり鉢との組み合わせが非常に重要です。
- サイズ:すり鉢の大きさに比べてすりこぎが短すぎると、手がすり鉢の縁に当たってしまい、使いにくくなります。逆に長すぎると、取り回しが悪くなることがあります。
- 素材:木製のすりこぎには、陶器製のすり鉢が一般的です。陶器製のすりこぎは、同じく陶器製のすり鉢と合わせると、より効率的に擂れることがあります。
- 選び方:すりこぎを選ぶ際は、今持っているすり鉢のサイズや素材を考慮しましょう。
4. お手入れのしやすさ
- ポイント:長く愛用するためには、お手入れのしやすさも重要な性能の一つです。
- 木製:使用後はすぐに水洗いし、しっかり乾燥させることが大切です。洗剤の使用は控えめにし、カビや匂い移りに注意が必要です。
- 陶器・ステンレス製:食洗機対応のものも多く、比較的簡単にお手入れできます。匂い移りの心配も少ないです。
- 選び方:ご自身のライフスタイルに合わせて、お手入れにかけられる時間や手間を考慮して選びましょう。
これらのポイントを総合的に検討することで、あなたの料理スタイルに最適なすりこぎを見つけることができるでしょう。
ぜひ、「これだ!」と思える一本を探してみてください。

すりこぎ棒 全長:90cm 木製 当り棒 大サイズ ごますり すりごま 胡麻和え 白和え ごますり 調理道具 家庭用 和食 材質:シナ材 定番 おすすめ 使いやすい すり棒 長い
価格:3080円 (2025/10/7時点)
楽天で詳細を見る
プロが選ぶ!すりこぎのおすすめメーカー&ブランド

すりこぎ選びにおいて、信頼できるメーカーやブランドを知ることは、品質の高い製品に出会うための近道です。
ここでは、プロも認めるおすすめのメーカーやブランドをいくつかご紹介します。
1. 伝統を継承する老舗木工メーカー
- 特徴:日本には、古くから木工技術を継承し、高品質な木製すりこぎを作り続けている老舗メーカーが多数存在します。
- 強み:厳選された木材(山椒、朴の木、檜など)を使用し、職人の手作業で一本一本丁寧に作られています。そのため、耐久性が高く、使い込むほどに手に馴染むのが特徴です。
- こんな人におすすめ:本格的な和食を追求したい方や、一生ものとして長く愛用したい方に最適です。
- 補足:特定のブランド名ではなく、「〇〇木工」「〇〇工芸」といった名称で探してみると良いでしょう。
2. モダンなデザインと機能性を追求するキッチンウェアブランド
- 特徴:国内外のキッチンウェアブランドの中には、伝統的なすりこぎに現代的な解釈を加え、デザイン性と機能性を両立させた製品を提供しているところもあります。
- 強み:ステンレスやセラミック、シリコンなど、多様な素材を使い、お手入れのしやすさや収納性にも配慮されています。スタイリッシュなデザインは、モダンなキッチンにもよく馴染みます。
- こんな人におすすめ:デザイン性を重視する方、手軽に使えるすりこぎを探している方にぴったりです。
- 補足:「OXO(オクソー)」や「貝印」など、幅広いキッチン用品を扱うブランドもチェックしてみる価値があります。
3. 素材に特化した専門ブランド
- 特徴:特定の素材(例:陶器、石)に特化し、その素材の特性を最大限に活かしたすりこぎを製造しているブランドもあります。
- 強み:例えば、石製のすりこぎは非常に重く、硬いスパイスやハーブを効率よく潰すのに優れています。陶器製は匂い移りが少なく、衛生的に使えるのが魅力です。
- こんな人におすすめ:特定の食材を専門的に扱いたい方や、素材の特性を活かした調理を楽しみたい方に良いでしょう。
- 補足:「モルタル&ペストル」といった海外の専門ブランドも選択肢に入れてみてもいいかもしれません。
これらのメーカーやブランドは、それぞれ異なる強みを持っています。
あなたの料理へのこだわりやライフスタイルに合わせて、最適なブランドを選んでみてください。
きっと、長く愛用できる素晴らしい一本に出会えるはずです。
もう迷わない!すりこぎの正しい使い方&メンテナンス

せっかく良いすりこぎを手に入れても、正しい使い方やメンテナンスを知らなければ、その性能を十分に引き出すことはできません。
ここでは、すりこぎを長く、そして快適に使うためのポイントを具体的に解説します。
すりこぎの正しい使い方
すりこぎは、ただゴリゴリと力を入れて擂れば良いというものではありません。
食材の特性に合わせて、力の入れ方や動かし方を工夫することで、より美味しく、効率的に調理できます。
- すり鉢を安定させる:すり鉢が動かないよう、濡れ布巾などを下に敷いて固定しましょう。
- 食材の入れ方:一度にたくさんの食材を入れると擂りにくくなります。少量ずつ加えながら擂るのがコツです。
- 擂り方(基本):すりこぎをすり鉢の底に当て、「の」の字を描くように回しながら、食材をすり鉢のギザギザに押し付けるように擂ります。
- ごまを擂る場合:
- 最初は軽く力を入れて、ごまの粒を潰すように擂ります。
- ごまが潰れてきたら、少しずつ力を強め、油分を引き出すように丁寧に擂りましょう。
- 焦らず、ゆっくりと擂ることで、香ばしさが格段に増します。
- 味噌を練る場合:
- 味噌をすり鉢に入れ、すりこぎで押し潰すように練り混ぜます。
- だし汁や他の調味料を加える際は、少しずつ加えてなめらかになるまで混ぜ合わせましょう。
すりこぎのメンテナンス方法
すりこぎを長く清潔に保つためには、使用後の適切なお手入れが不可欠です。
- 使用後すぐに洗う:食材が乾燥してこびりつく前に、すぐに水で洗い流しましょう。
- 木製すりこぎの場合:
- 洗剤は控えめに:木材は洗剤を吸収しやすく、匂いが残ることがあります。基本的には水洗いで十分です。
- しっかり乾燥させる:洗い終わったら、風通しの良い場所で完全に乾燥させましょう。湿気が残るとカビの原因になります。直射日光はひび割れの原因になることがあるので避けましょう。
- 匂い移り対策:匂いの強い食材を擂った後は、重曹水に浸けておくと匂いが取れやすくなります。
- 陶器・ステンレス製すりこぎの場合:
- 洗剤使用OK:通常の食器用洗剤で洗うことができます。食洗機対応のものも多いです。
- 乾燥:清潔な布で拭くか、自然乾燥させましょう。
- 保管方法:
- 湿気の少ない場所で保管しましょう。
- 木製の場合は、吊るして保管すると、より乾燥しやすく衛生的です。
これらの使い方とメンテナンスを実践することで、あなたのすりこぎはいつまでも最高のパフォーマンスを発揮し、料理の良きパートナーとして活躍してくれるでしょう。
後悔しないために!購入前の注意点とよくある失敗
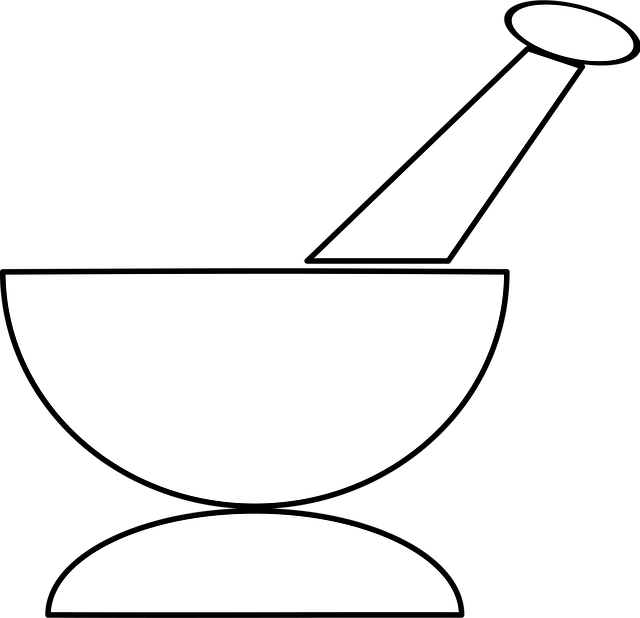
すりこぎ選びは、一見シンプルに見えても、いくつかの落とし穴があります。
購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、事前に知っておくべき注意点とよくある失敗例を解説します。
購入前の注意点
- すり鉢とのサイズ合わせは必須!
- 注意点:すりこぎとすり鉢のサイズが合っていないと、効率的に擂ることができません。すりこぎが短すぎると手がすり鉢の縁に当たり、長すぎると取り回しが悪くなります。
- 回避策:購入前に、現在お持ちのすり鉢の直径と深さを測り、それに合った長さのすりこぎを選びましょう。理想は、すりこぎの先端がすり鉢の底にしっかり届き、持ち手がすり鉢の縁から適度に出る長さです。
- 素材の特性を理解する
- 注意点:木製は匂いが移りやすく、カビが生えやすい。陶器製は割れやすい。ステンレス製は擂り心地が物足りないと感じることもあります。
- 回避策:それぞれの素材のメリット・デメリットを理解した上で、ご自身の用途やお手入れの頻度に合わせて選びましょう。例えば、匂い移りが気になるなら陶器製、本格的な風味を求めるなら木製といった具合です。
- 収納スペースを考慮する
- 注意点:意外と見落としがちなのが、収納スペースです。特に長いすりこぎは、引き出しや棚に収まらないことがあります。
- 回避策:購入前に、収納場所のサイズを測っておくと安心です。吊り下げ収納ができるタイプや、コンパクトなものを選ぶのも良いでしょう。
よくある失敗例とその回避策
- Q: 「買ったはいいけど、結局使わなくなってしまった…」
- A: 手入れが面倒だったり、使いこなせないと感じたりすることが原因です。
回避策:購入前に、どんな料理に使うか具体的にイメージし、お手入れのしやすさも考慮して選びましょう。最初は手軽な陶器製から始めてみてもいいかもしれません。
- Q: 「ごまがなかなか擂れない!力がいるし疲れる…」
- A: すりこぎの先端の溝が浅すぎたり、持ち手が握りにくかったりすることが原因です。また、すり鉢のギザギザ(目立て)が摩耗している可能性もあります。
回避策:溝がしっかりしている山椒の木製すりこぎや、手にフィットする太さ・重さのものを選びましょう。すり鉢の目立てが甘い場合は、新しいすり鉢の購入も検討してみてもいいかもしれません。
- Q: 「木製すりこぎにカビが生えてしまった…」
- A: 使用後にしっかり乾燥させていなかったことが主な原因です。
回避策:使用後はすぐに水洗いし、風通しの良い場所で完全に乾燥させましょう。湿気の多い場所での保管は避け、吊るして保管するなどの工夫をしてみてもいいかもしれません。
これらの注意点と失敗例を参考に、賢くすりこぎを選び、後悔のない購入をしてください。
きっと、あなたのキッチンに長く寄り添う一本が見つかるはずです。
まとめ:すりこぎで最高の体験を手に入れよう!
この記事では、すりこぎの基本的な特徴から、種類、選び方のポイント、おすすめメーカー、そして正しい使い方やメンテナンス方法、さらには購入前の注意点まで、幅広く解説してきました。
すりこぎは、単なる調理器具ではありません。
食材の本来の風味を最大限に引き出し、料理に深みと愛情を添える、魔法のような存在です。
手作業で丁寧に擂り潰す時間は、心を落ち着かせ、料理の楽しさを再発見させてくれるでしょう。
この記事を参考に、あなたのライフスタイルや料理へのこだわりにぴったりのすりこぎを見つけて、毎日の食卓をさらに豊かにしてください。
最高のすりこぎを手に入れ、「作ってよかった」「食べてよかった」と心から思える、最高の料理体験をぜひ手に入れてみませんか。
さあ、あなたも今日からすりこぎのある豊かな食生活を始めてみましょう!






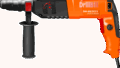

コメント